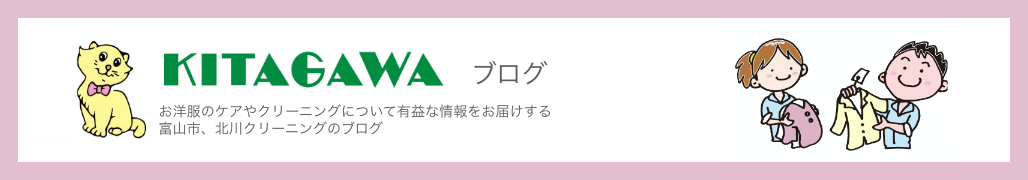こんにちは、kittanです!
衣服の変色は、日常生活の中で意外と見逃されがちです。
時間が経ってから色落ちや黄ばみ、シミなどに気づいて、驚いたことはありませんか?
衣服が変色しやすい要因を知っておけば、大切な衣服を長くきれいに保つことができます。
今回は、特に注意したい6つのシーンをご紹介します。
① 汗が衣服を変色させる?
汗には99%の水分のほかに、塩分や乳酸、尿素などが含まれています。
水分は蒸発しますが、水分以外の成分は汗をかくたびにお洋服の繊維の間に
蓄積されてしまいます。
特に脇の下などの汗は、他の部分の汗よりもタンパク質などの成分が濃厚なため、
天然繊維などの素材や衣服の染料に影響を与え、変退色の原因になるだけでなく、
生地は破れやすくなってしまいます。
② 汗と紫外線の複合作用で衿が変退色!
ワイシャツやブラウスなどの衿は、首周りを覆う扇状の台衿に支えられています。
首から出た汗は、接触している台衿に吸収され、表側の衿に浸透していきます。
その結果、衿の縁に沿って衿の色や柄があせているものを見かけることがあります。
しかし不思議なことに、汗を吸収しているはずの衿の内側(衿裏)は変退色していません。
これは、汗の成分が紫外線を受けることで、表側の衿の染料を分解させてしまうために起こる現象です。
汗によるダメージを最小限に抑えるには、汗を吸った衣服を早めに洗うことや、直射日光に長時間さらさない工夫が効果的です。
③ 消毒アルコールを使用したとき
手指の消毒に使われるアルコール(エタノール消毒液)や香水には、揮発性の高いエタノールが含まれています。
これらが洋服に直接付着すると、染料を分解して脱色や変色を引き起こすことがあります。
特に濃い色の衣類は影響を受けやすいため、アルコール消毒を使用する際は、袖口など服に触れやすい部分に注意が必要です。
④ 掃除で衣服を変色させてしまう?
お風呂場のカビ取り剤やキッチンの除菌用漂白剤、トイレ洗剤などには次亜塩素酸ナトリウムが含まれています。
スプレー式の薬剤がウール、シルクなどのタンパク質繊維につくと生地を溶解してしまいます。
植物繊維(コットンや麻など)の場合は、生地の退色、変色の原因になります。
すぐには変色や脱色が起きなくても、洗濯後のアイロンの熱や乾燥機の熱に反応すると色が抜けてしまいます。
お掃除の際は汚れても良い服装で作業しましょう。
また、ショッピングモールや駅などの公共施設のトイレはお掃除中や洗浄中でも
利用できるようになっている場合が増えました。洋式のトイレの便座周辺や
床面などに洗浄剤が残っていると、ジャケットの裾、ズボンやスカートなどに吸収されて、
変色や脱色することがあります。お気をつけくださいね。
⑤ シミを布のおしぼりで拭いてしまったとき食事や飲み会の時に洋服にシミがついてしまい、思わずおしぼりで拭いてしまうということはありませんか?
実は、布のおしぼりには漂白剤の成分が含まれています。
おしぼりは規定によって塩素系漂白剤で消毒するように義務付けられているためです。
また、保管中に細菌が繁殖しないように、ある程度の漂白成分が残されています。
そのため、食事中に衣服についたシミをおしぼりで取ろうとすると、生地の色が落ちてしまう可能性があるのでご注意下さい。
⑥ 美容院でパーマをかけるとき
パーマ液の薬液は衣服の染料に強い影響力を持っています。
パーマ液は一見すると薄い水溶液ですが、衣類に薬剤が付着すると、すぐに変色しない場合でも注意が必要です。
と言うのは、クリーニング後や保管中に化学変化が進み、時間が経ってから変色が現れることがあるためです。
衿周りや肩などの一部が濃いこげ茶や赤紫色に変色している場合、そのお洋服を美容院に着て行かなかったかどうかを思い出してみましょう。
美容院では通常十分に配慮していますが、念のために多少変色があっても構わないような普段着で出かける方が安心です。
以上が、日常生活の中でよく見受けられる衣服に変色のできやすいシーンです。
どの様な行動が衣服にダメージを与えるかを知ることにより、変色や脱色のリスクからご自分のお洋服をお守り下さいね。